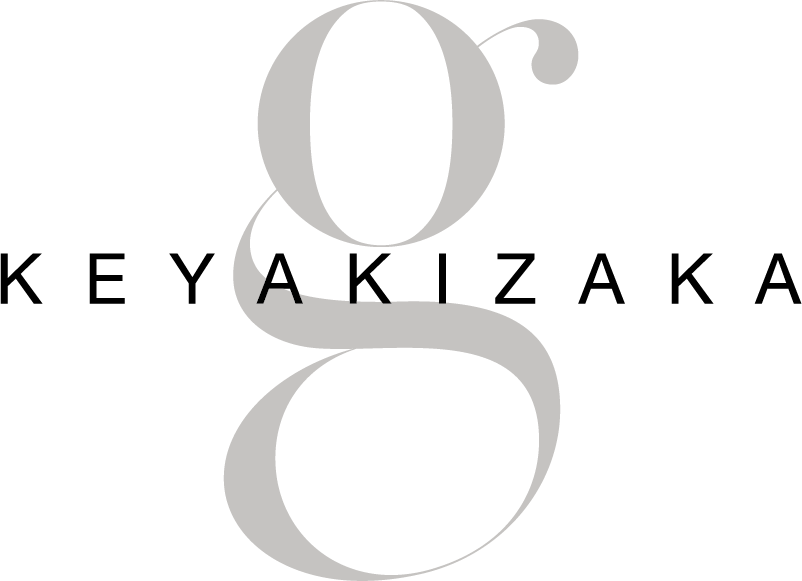バイヤー手記

第5回 福井出張 2日目 ③
福井出張2日目 森國清寛氏のもとへ 出張2日目、私は刀鍛冶・森國清寛氏を訪ねました。 年間24本しか打てないという厳しい制約の中で、氏はお一人で製作を続けており、その上限に達することは決して容易ではありません。 しかし、氏の手から生み出される作品は、刀という枠を超えてもなお、圧倒的な存在感と力強さを持っています。 今回の訪問は、そんな氏の作品を刀以外の形でも表現できないか、ご相談することが目的でした。 氏とは、第3回目のイベントでご縁をいただき、作品をお貸しいただいた経緯があります。 今回も第4回目のイベントに向け、再び氏の作品をお借りするお願いを兼ねての訪問です。 今回、氏の手元にあるモデルとなる刀を拝見させていただきました。 前回お借りした刀は繊細で優美、正に美術品としての洗練された印象が強いものでしたが、今回は鎌倉時代に作られた太刀の写し。 厚みのある刀身は、まさに実戦を想起させる力強さを感じさせ、ほんの数センチの違いでここまで印象が変わるのかと、素人目にもその迫力が伝わってきました。 また、今回の訪問では、玉鋼から刀へと鍛え上げる工程の中で生まれる"区切りの産物"についてもお話を伺いました。 通常、これらは商品として表に出ることはありませんが、実際に拝見したその素材は、玉鋼の持つ独特の表情と、変容していく過程の痕跡が生きており、まるで無機物でありながら有機物のような生命感を感じさせるものでした。 氏の手の跡が如実に残るその素材は、私の想像力をかき立て、すでにいくつかのアイディアが浮かび上がっています。 ...
第5回 福井出張 2日目 ③
福井出張2日目 森國清寛氏のもとへ 出張2日目、私は刀鍛冶・森國清寛氏を訪ねました。 年間24本しか打てないという厳しい制約の中で、氏はお一人で製作を続けており、その上限に達することは決して容易ではありません。 しかし、氏の手から生み出される作品は、刀という枠を超えてもなお、圧倒的な存在感と力強さを持っています。 今回の訪問は、そんな氏の作品を刀以外の形でも表現できないか、ご相談することが目的でした。 氏とは、第3回目のイベントでご縁をいただき、作品をお貸しいただいた経緯があります。 今回も第4回目のイベントに向け、再び氏の作品をお借りするお願いを兼ねての訪問です。 今回、氏の手元にあるモデルとなる刀を拝見させていただきました。 前回お借りした刀は繊細で優美、正に美術品としての洗練された印象が強いものでしたが、今回は鎌倉時代に作られた太刀の写し。 厚みのある刀身は、まさに実戦を想起させる力強さを感じさせ、ほんの数センチの違いでここまで印象が変わるのかと、素人目にもその迫力が伝わってきました。 また、今回の訪問では、玉鋼から刀へと鍛え上げる工程の中で生まれる"区切りの産物"についてもお話を伺いました。 通常、これらは商品として表に出ることはありませんが、実際に拝見したその素材は、玉鋼の持つ独特の表情と、変容していく過程の痕跡が生きており、まるで無機物でありながら有機物のような生命感を感じさせるものでした。 氏の手の跡が如実に残るその素材は、私の想像力をかき立て、すでにいくつかのアイディアが浮かび上がっています。 ...

福井出張 2日目 ②
10年に1度といわれる寒波が巻き起こす大雪の日、雪に覆われた道を進みながら、山田 大氏のもとを訪れた。今回迎えてくださったのは、ご自宅の一室。厳しい寒さの中にもかかわらず、温かく迎え入れてくださった山田氏。部屋には、父である山田 和氏と共に築き上げた陶芸の作品が息づいていた。 山田 大氏は、桃山陶をベースにした志野・瀬戸黒・伊賀・南蛮などを手掛け、自ら築いた穴窯で独特の焼成を施している。その作品は、古陶のような重厚な風合いと、時代を超えた美しさを併せ持つ。彼は「本物の志野」を追求し続け、食や文化、人との関わりにまで思索を巡らせることで作品に奥行きを与えていた。彼の作品に触れながら、一つの道を究めることで、自然と他の分野にも審美眼が養われるのではないかと感じた。陶芸のみならず、食や文化への広範な視点を持ち、学びを深めることで作品に新たな表情を生み出している。その姿勢が、単なる器作りを超えた芸術的探求へと繋がっているように思えた。 また、彼との対話は、理論的でありながらも情熱に満ち、作品に込めた想いや背景を深く知ることができる貴重な時間だった。さらに、こちらの意図を汲み取り、快く提案をしてくださる柔軟さと優しさも感じられた。帰り道、降り積もる雪の中で、彼との静かで豊かな時間を思い返した。単なる打合せの場ではなく、思索を交わす場。その変化を内包し続ける山田氏の作品が店頭に並ぶことを心から楽しみにしつつ、次に訪れる日を待ち望む気持ちになった。
福井出張 2日目 ②
10年に1度といわれる寒波が巻き起こす大雪の日、雪に覆われた道を進みながら、山田 大氏のもとを訪れた。今回迎えてくださったのは、ご自宅の一室。厳しい寒さの中にもかかわらず、温かく迎え入れてくださった山田氏。部屋には、父である山田 和氏と共に築き上げた陶芸の作品が息づいていた。 山田 大氏は、桃山陶をベースにした志野・瀬戸黒・伊賀・南蛮などを手掛け、自ら築いた穴窯で独特の焼成を施している。その作品は、古陶のような重厚な風合いと、時代を超えた美しさを併せ持つ。彼は「本物の志野」を追求し続け、食や文化、人との関わりにまで思索を巡らせることで作品に奥行きを与えていた。彼の作品に触れながら、一つの道を究めることで、自然と他の分野にも審美眼が養われるのではないかと感じた。陶芸のみならず、食や文化への広範な視点を持ち、学びを深めることで作品に新たな表情を生み出している。その姿勢が、単なる器作りを超えた芸術的探求へと繋がっているように思えた。 また、彼との対話は、理論的でありながらも情熱に満ち、作品に込めた想いや背景を深く知ることができる貴重な時間だった。さらに、こちらの意図を汲み取り、快く提案をしてくださる柔軟さと優しさも感じられた。帰り道、降り積もる雪の中で、彼との静かで豊かな時間を思い返した。単なる打合せの場ではなく、思索を交わす場。その変化を内包し続ける山田氏の作品が店頭に並ぶことを心から楽しみにしつつ、次に訪れる日を待ち望む気持ちになった。

第5回 福井出張 2日目
福井出張2日目の朝。 東京ではあまり見ることができない大雪に見舞われ、本当にこんな中で移動ができるのかと不安でいっぱいだった。 しかし、さすが雪国。 同乗させていただいた車は、雪道でも驚くほどスムーズに進み、無事に熊野九郎右ヱ門氏のアトリエへ到着した。 ガレージには雪が積もっており、ほんの数メートル歩くだけでも雪に足を取られ、冷たい空気が身にしみる。 それでもアトリエの扉を開けた瞬間、別世界が広がっていた。 室内には薪ストーブが赤々と燃えており、その柔らかな温かさが心まで温めてくれる。 大きく開いた窓からは絶え間なく雪が降り続いており、外の厳しさが薪ストーブの暖かさを一層際立たせていた。 氏のもてなしは、暖かさだけでなく、人格の大きさや懐の深さを感じさせるものだった。お話を伺ううちに、外の世界とは対照的に、心地よく穏やかな時間が流れていく。 今回の訪問の目的は、3月に実施する茶事のイベントで使用する抹茶盌のお貸出しについての依頼だった。 まだ2回目の訪問でしかない私の厚かましいお願いにもかかわらず、氏は熱心にイベントの詳細を尋ねてくださり、まだ確定していない部分も多い中、私の考えを丁寧にお伝えした。 すると氏は奥様に向かって「あの抹茶盌を持ってきてほしい」と頼まれ、一つの抹茶盌が私の手元に渡された。 現在店頭でお預かりしている抹茶碗は、どれも個性豊かな作品ばかりだが、今回用意してくださった抹茶盌は、表現として適切かはわからないが、まるで清楚で美しい女性を思わせる佇まいだった。 和やかな雰囲気の中、氏の若い頃の破天荒なエピソードや、歴史・地理への深い造詣、長年の研究から導き出された哲学についてお話を伺い、貴重で楽しいひとときを過ごすことができた。 また、別件として弊社が依頼しているTENOHA MILANOでの展示についても話題に上がった。 昨日、別のチームが訪問していたこともあり、その件について改めて問い合わせを受けた。 限られた情報の中で丁寧に説明すると、氏は紙と鉛筆を取り出し、現在金津創作の森美術館に展示中の七点の作品をスラスラと描き上げてくださった。 そのラフスケッチは、特徴がしっかりと表現されており、温かみと力強さを併せ持つ素晴らしいものだった。...
第5回 福井出張 2日目
福井出張2日目の朝。 東京ではあまり見ることができない大雪に見舞われ、本当にこんな中で移動ができるのかと不安でいっぱいだった。 しかし、さすが雪国。 同乗させていただいた車は、雪道でも驚くほどスムーズに進み、無事に熊野九郎右ヱ門氏のアトリエへ到着した。 ガレージには雪が積もっており、ほんの数メートル歩くだけでも雪に足を取られ、冷たい空気が身にしみる。 それでもアトリエの扉を開けた瞬間、別世界が広がっていた。 室内には薪ストーブが赤々と燃えており、その柔らかな温かさが心まで温めてくれる。 大きく開いた窓からは絶え間なく雪が降り続いており、外の厳しさが薪ストーブの暖かさを一層際立たせていた。 氏のもてなしは、暖かさだけでなく、人格の大きさや懐の深さを感じさせるものだった。お話を伺ううちに、外の世界とは対照的に、心地よく穏やかな時間が流れていく。 今回の訪問の目的は、3月に実施する茶事のイベントで使用する抹茶盌のお貸出しについての依頼だった。 まだ2回目の訪問でしかない私の厚かましいお願いにもかかわらず、氏は熱心にイベントの詳細を尋ねてくださり、まだ確定していない部分も多い中、私の考えを丁寧にお伝えした。 すると氏は奥様に向かって「あの抹茶盌を持ってきてほしい」と頼まれ、一つの抹茶盌が私の手元に渡された。 現在店頭でお預かりしている抹茶碗は、どれも個性豊かな作品ばかりだが、今回用意してくださった抹茶盌は、表現として適切かはわからないが、まるで清楚で美しい女性を思わせる佇まいだった。 和やかな雰囲気の中、氏の若い頃の破天荒なエピソードや、歴史・地理への深い造詣、長年の研究から導き出された哲学についてお話を伺い、貴重で楽しいひとときを過ごすことができた。 また、別件として弊社が依頼しているTENOHA MILANOでの展示についても話題に上がった。 昨日、別のチームが訪問していたこともあり、その件について改めて問い合わせを受けた。 限られた情報の中で丁寧に説明すると、氏は紙と鉛筆を取り出し、現在金津創作の森美術館に展示中の七点の作品をスラスラと描き上げてくださった。 そのラフスケッチは、特徴がしっかりと表現されており、温かみと力強さを併せ持つ素晴らしいものだった。...

第5回 福井出張 1日目 ②
福井出張 1日目 昆布屋孫兵衛 2件目は、昆布屋孫兵衛さまへの訪問です。 ここでは井上徳木工の井上氏と待ち合わせ、昆布氏、井上氏、そして私の3者で打ち合わせを行いました。 今回のテーマは、第4回ポップアップイベントで提供するお菓子についてのご相談です。 昆布屋孫兵衛さまには、第1回目の福井ポップアップで商品を供給していただきました。 しかし、昆布氏が「何か面白いことをやりたい」という情熱をお持ちであることから、ただ商品を提供するだけでは、その想いに応えられないのではないかと考え、2回目と3回目のポップアップではお声がけを控えていました。 しかし、最後となる第4回目のポップアップでは、昆布氏に「面白い」と言っていただける企画を携えて、緊張しながらの訪問となりました。 井上氏の力を借りて製作したオリジナルの器「苔鈍(こけにび)」の色見本と形状見本をお持ちし、昆布氏に企画の詳細と担っていただきたい役割を丁寧に説明しました。 その結果、昆布氏から「とても面白い取り組み」と評価していただき、胸をなでおろしました。 その喜びが冷めやらぬまま、店頭に並ぶお菓子をついつい買い求めてしまいました。 そして、なんと昆布氏ご自身が製作されたケーキをお土産にいただくという嬉しいサプライズも! 今、ホテルの一室でこの原稿を書いていますが、打ち合わせの成功といただいたお土産の喜びが余韻として心に残っています。 これからそのケーキを味わうため、筆を置くことにします。
第5回 福井出張 1日目 ②
福井出張 1日目 昆布屋孫兵衛 2件目は、昆布屋孫兵衛さまへの訪問です。 ここでは井上徳木工の井上氏と待ち合わせ、昆布氏、井上氏、そして私の3者で打ち合わせを行いました。 今回のテーマは、第4回ポップアップイベントで提供するお菓子についてのご相談です。 昆布屋孫兵衛さまには、第1回目の福井ポップアップで商品を供給していただきました。 しかし、昆布氏が「何か面白いことをやりたい」という情熱をお持ちであることから、ただ商品を提供するだけでは、その想いに応えられないのではないかと考え、2回目と3回目のポップアップではお声がけを控えていました。 しかし、最後となる第4回目のポップアップでは、昆布氏に「面白い」と言っていただける企画を携えて、緊張しながらの訪問となりました。 井上氏の力を借りて製作したオリジナルの器「苔鈍(こけにび)」の色見本と形状見本をお持ちし、昆布氏に企画の詳細と担っていただきたい役割を丁寧に説明しました。 その結果、昆布氏から「とても面白い取り組み」と評価していただき、胸をなでおろしました。 その喜びが冷めやらぬまま、店頭に並ぶお菓子をついつい買い求めてしまいました。 そして、なんと昆布氏ご自身が製作されたケーキをお土産にいただくという嬉しいサプライズも! 今、ホテルの一室でこの原稿を書いていますが、打ち合わせの成功といただいたお土産の喜びが余韻として心に残っています。 これからそのケーキを味わうため、筆を置くことにします。

第5回 福井出張 1日目
福井出張1日目 滝製紙所 福井への出張も今回で5回目。 今回の3日間の旅は、これまでお世話になった取引先へのご挨拶から始まりました。 顔なじみの皆様と再会するたびに、福井の温かさを改めて感じます。 初日のハイライトは、滝製紙所さまへの訪問。 3月に開催予定の第4回福井ポップアップで、最も重要な店装について瀧氏とご相談するためです。工房に到着すると、瀧氏がわざわざこの日のために用意してくださった和紙のサンプルが迎えてくれました。 こちらのイメージ通りの仕上がりに感動し、打ち合わせは終始スムーズに進行。 さらに、私が思いもよらなかった細部にまで心を配った提案の数々に、驚きと感謝の気持ちでいっぱいになりました。 店装のイメージが明確になり、ほっと一息ついたところで、次は店頭展開する商品のご相談です。 瀧氏からは、私の想像を超える素晴らしいアイディアと魅力的な商品を次々とご提案いただき、静かな興奮が心を満たしました。 これらの新しいサービスや商品は、第4回ポップアップで皆様にお披露目できるよう、これから準備を進めてまいります。 お楽しみに。 そして最後に、滝製紙所の工房を見学。外の冷たい空気が差し込む広々とした空間に足を踏み入れると、「ここであの美しい和紙が生まれるのだ」と感慨深くなります。初めての和紙製作現場ではないので、細部まではわかりませんが特別な道具が並んでいるわけではありません。それでも、なぜこれほど素晴らしい作品が生まれるのか——その答えは、やはり「人のセンス」にあると強く感じました。 瀧氏は、私が目指す姿の遥か先を走る、まさに理想の作り手。今回の訪問で、彼への尊敬の念が一層深まりました。 今はまだお伝えできないことも多いですが、たくさんのアイディアが形となり、g KEYAKIZAKAでお披露目される日が近づいています。 その日を、どうぞ楽しみにお待ちください。
第5回 福井出張 1日目
福井出張1日目 滝製紙所 福井への出張も今回で5回目。 今回の3日間の旅は、これまでお世話になった取引先へのご挨拶から始まりました。 顔なじみの皆様と再会するたびに、福井の温かさを改めて感じます。 初日のハイライトは、滝製紙所さまへの訪問。 3月に開催予定の第4回福井ポップアップで、最も重要な店装について瀧氏とご相談するためです。工房に到着すると、瀧氏がわざわざこの日のために用意してくださった和紙のサンプルが迎えてくれました。 こちらのイメージ通りの仕上がりに感動し、打ち合わせは終始スムーズに進行。 さらに、私が思いもよらなかった細部にまで心を配った提案の数々に、驚きと感謝の気持ちでいっぱいになりました。 店装のイメージが明確になり、ほっと一息ついたところで、次は店頭展開する商品のご相談です。 瀧氏からは、私の想像を超える素晴らしいアイディアと魅力的な商品を次々とご提案いただき、静かな興奮が心を満たしました。 これらの新しいサービスや商品は、第4回ポップアップで皆様にお披露目できるよう、これから準備を進めてまいります。 お楽しみに。 そして最後に、滝製紙所の工房を見学。外の冷たい空気が差し込む広々とした空間に足を踏み入れると、「ここであの美しい和紙が生まれるのだ」と感慨深くなります。初めての和紙製作現場ではないので、細部まではわかりませんが特別な道具が並んでいるわけではありません。それでも、なぜこれほど素晴らしい作品が生まれるのか——その答えは、やはり「人のセンス」にあると強く感じました。 瀧氏は、私が目指す姿の遥か先を走る、まさに理想の作り手。今回の訪問で、彼への尊敬の念が一層深まりました。 今はまだお伝えできないことも多いですが、たくさんのアイディアが形となり、g KEYAKIZAKAでお披露目される日が近づいています。 その日を、どうぞ楽しみにお待ちください。

福井出張 2日目②
ー第4回目の福井出張手記:アートと伝統工芸品の融合 2日目-② ー 続いては福井工業大学へ。 母校というわけではないけれど、大学という施設に足を運ぶのは実に30年ぶり。 懐かしい空気が漂うキャンパスに一歩足を踏み入れ、ふくいアンテナショップ291プレミアムの3回目のテーマ「アートと工芸との融合」について、”AsCアーツ&コミュニティふくい”の浅野さまと坂田さまと打合せを行うことになりました。 打合せが始まると、浅野さまと坂田さまの温かい笑顔に迎えられ、会話はすぐに和やかな雰囲気に包まれました。 最初の話題は「越前和紙の定義」でした。 浅野さまは、越前和紙として作品を発表することに違和感を感じているとのこと。 この点について、坂田さまは伝統的な工芸品としての越前和紙と、ブランドとしての越前和紙の2つの側面が存在することをご説明いただきました。 ブランド化された越前和紙が現代においてどのように位置づけられるべきか、新たな命名や発信方法を模索する必要があるという結論に至りました。 私も、「越前和紙の文脈の中で新しい名前をつけるか、あるいは問いかけとして提示することで、より深い意味合いを持たせることができるのではないか」と提案し、話が広がっていきました。 越前和紙の歴史や技術とアートとして新しい作品が生まれる文脈について深い議論が交わされ、その素晴らしさに改めて感銘を受けました。 次に、展示方法についての議論に移りました。 浅野さまの作品構想は、漉いたばかりの和紙を福井県内のあらゆる箇所に貼り付けて乾いた後、剥がす。 剥がした和紙には写し取った壁、地面、柱、その他様々なモノが経てきた空気や質感の魅力を最大限に引き出す効果的な手法だと強調されました。 『福井県の空気』を持ってくると表現されました。 また、作品サイズについても話し合われ、900×900mmの大きな作品からA3サイズの小さな作品まで、多様な展示が計画されていることが確認されました。 展示の際にはフレームを付けず、購入者の要望に応じて額装する柔軟な対応も可能であることが共有され、実際の展示がますます楽しみになりました。 最後に、展示の記録の重要性についての話し合いがありました。 坂田さまは、展示物の制作過程や展示の準備の記録をしっかりと残すことが後々のプロモーションに役立つと強調され、浅野さまもこれに賛同。 私も、今後の広報活動やドキュメント制作に向けて、具体的な記録手法の検討が必要であると述べ、次のステップに進むことになりました。 ...
福井出張 2日目②
ー第4回目の福井出張手記:アートと伝統工芸品の融合 2日目-② ー 続いては福井工業大学へ。 母校というわけではないけれど、大学という施設に足を運ぶのは実に30年ぶり。 懐かしい空気が漂うキャンパスに一歩足を踏み入れ、ふくいアンテナショップ291プレミアムの3回目のテーマ「アートと工芸との融合」について、”AsCアーツ&コミュニティふくい”の浅野さまと坂田さまと打合せを行うことになりました。 打合せが始まると、浅野さまと坂田さまの温かい笑顔に迎えられ、会話はすぐに和やかな雰囲気に包まれました。 最初の話題は「越前和紙の定義」でした。 浅野さまは、越前和紙として作品を発表することに違和感を感じているとのこと。 この点について、坂田さまは伝統的な工芸品としての越前和紙と、ブランドとしての越前和紙の2つの側面が存在することをご説明いただきました。 ブランド化された越前和紙が現代においてどのように位置づけられるべきか、新たな命名や発信方法を模索する必要があるという結論に至りました。 私も、「越前和紙の文脈の中で新しい名前をつけるか、あるいは問いかけとして提示することで、より深い意味合いを持たせることができるのではないか」と提案し、話が広がっていきました。 越前和紙の歴史や技術とアートとして新しい作品が生まれる文脈について深い議論が交わされ、その素晴らしさに改めて感銘を受けました。 次に、展示方法についての議論に移りました。 浅野さまの作品構想は、漉いたばかりの和紙を福井県内のあらゆる箇所に貼り付けて乾いた後、剥がす。 剥がした和紙には写し取った壁、地面、柱、その他様々なモノが経てきた空気や質感の魅力を最大限に引き出す効果的な手法だと強調されました。 『福井県の空気』を持ってくると表現されました。 また、作品サイズについても話し合われ、900×900mmの大きな作品からA3サイズの小さな作品まで、多様な展示が計画されていることが確認されました。 展示の際にはフレームを付けず、購入者の要望に応じて額装する柔軟な対応も可能であることが共有され、実際の展示がますます楽しみになりました。 最後に、展示の記録の重要性についての話し合いがありました。 坂田さまは、展示物の制作過程や展示の準備の記録をしっかりと残すことが後々のプロモーションに役立つと強調され、浅野さまもこれに賛同。 私も、今後の広報活動やドキュメント制作に向けて、具体的な記録手法の検討が必要であると述べ、次のステップに進むことになりました。 ...